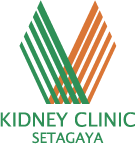第149回 元気で長生き講座【2025年3月号】
~八潮市の道路陥没事故と透析施設からの排水とは無関係です~
2025年1月、埼玉県八潮市で大規模な道路陥没事故が発生しました。事故原因として下水道管の破裂が指摘される中、過去に北海道、兵庫県や東京都内にて適切な中和処理がなされていなかった透析施設からの酸性排水による下水道管の損傷事故事例がある1)ことから、一部では埼玉地域の透析施設からの強酸性排水が下水道管の劣化を招き、事故につながったのではないかとの憶測がなされています。ここでは、技術的・科学的観点から両者の関連性を検証し、下水道管の破裂と透析施設からの排水が無関係であることを示します。
事故は2025年1月30日未明、八潮市内の幹線道路下で発生しました。陥没穴は最大幅40メートル、深さ15メートルに達し、トラックが転落する事態となりました。原因として、地下10メートルに埋設されていた直径4.75メートルの鉄筋コンクリート製下水道管の破損が考えられています。この下水道管は1983年に敷設され、耐用年数50年のうち42年が経過していました。
調査結果によると、破損した下水道管は老朽化による材質の脆弱化が確認され、特に以下の要因が影響を及ぼしたとされています2)。
①経年劣化:事故現場の下水道管は敷設後42年が経過し、管材の劣化が進行していた。
②外部要因:道路交通による振動や地盤変動の影響が蓄積されていた。
③接合部の劣化:ジョイント部分のシール材の劣化が見られ、そこから水が漏れ続けた可能性がある。
④地下水位の変動:近年の異常気象や地盤沈下により地下水位が変動し、管周囲の土壌が侵食され支持力が低下した可能性がある。
⑤下水の硫化水素による腐食:下水中の有機物が分解される過程で発生する硫化水素(H₂S)が管内のコンクリートや鉄筋を腐食し、強度を低下させた可能性がある。
⑥地盤の脆弱性:事故現場の地盤が埋立地や沖積層だった場合、もともと支持力が低く、わずかな振動や水の流れで流動化した可能性がある。
⑦施工不良・設計上の問題:1983年施工の管であるため、当時の施工基準や工法が現代の基準と異なっていた可能性があり、コンクリートの質や鉄筋の配置に問題があった可能性も考えられる。
透析施設では、透析液の廃棄により排水が発生しますが、以下の理由から下水道管の劣化に及ぼす影響は限定的であり、陥没事故とは無関係であると考えられます。まず、日本の下水道法3)では、事業活動による排水のpH値は5.8〜8.6に制限されています。透析施設からの排水は、この基準を満たすように中和処理が義務付けられており、各透析施設の中和処理により強酸性の排水が直接下水道に流入することはありません。また、本院で実施しております在宅血液透析(HHD)実施中の患者様のご自宅からの透析排水は、総下水量のごく一部であり、下水道全体で希釈されます。たとえpHの低い排水が流入したとしても、大量の生活排水や工業排水と混合されることで中和されるため、局所的な影響はほぼありません。本陥没事故の原因として前述の通り硫化水素が言われており、硫化水素は気体のため、下水道管上部を腐食させ、実際下水道管上部に大きな穴が生じましたが、強酸性の排水が仮に原因とすれば下水道管上部ではなく下部を腐食させるため、そもそも原因が異なることが考えられます。
したがって、八潮市の陥没事故は、老朽化した下水道管の破裂および地盤の脆弱性が原因として考えられ、透析施設の排水とは無関係です。透析施設の排水は法規制により適切に処理されており、下水道管を急速に劣化させる要因とはなり得ません。本事故現場の発生状況を考慮すると、仮にpHの変動があったとしても、事故の直接的な原因とはなり得ません。そして何より、事故現場近くに透析施設が存在しない(最も近くて2km以上離れている)ことから、透析施設の排水が下水道管の劣化や本陥没事故に関与した可能性は否定されます。以上の点から、透析施設の排水が八潮市の陥没事故に影響を及ぼしたとの主張には、科学的根拠がないことが明らかです。
なお本院は2008年の開業時よりpHを中和する日機装社製中和処理装置を本院敷地内に設置しており、また2021年7月から「洗浄剤の変更による対応」や「透析排液の緩衝能を利用した中和による対応」を東京都水道局が承認した4)ことを受け、中性洗浄剤に変更して一定期間のモニタリングを行いました。その結果排水のpHが法定内に保たれていたため、2022年7月22日に下水道局に対し水質改善報告書を提出し受理されております。そしてその調査結果を「本院における排水基準達成に向けた取り組み」と題して、2023年の日本血液浄化技術学会にて山田臨床工学技士が発表5)していることを、ここにご報告いたします。
適切な中和処理が行われておりますのでご安心ください。
参考URL/文献
1) 安部 貴之, 花房 規男, 土谷 健, 市場 晋吾, 星野 純一:【新人CEのための透析装置の基礎入門】透析排水管理 中和装置・中性洗浄剤.Clinical Engineering35巻5号 Page453-462, 20242)
2) 東洋経済オンライン「日本の下水道管」を劣化させている6つの要素. 2025年2月4日
4) 宍戸 寛治, 日本透析医学会学術委員会透析排水管理ワーキンググループ:透析排水問題―早期の現実的な解決に向けて―.日本透析医会雑誌36巻3号 Page434-439, 20215)
5)山田遥香, 西澤喬光, 竹石康広, 斉藤祐太, 菅沼信也: 本院における排水基準達成に向けた取り組み. 日本血液浄化技術学会雑誌 (Journal of Japanese Society for Technology of Blood Purification)32巻Suppl.Page189,2024